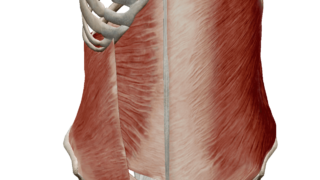こんにちは。
理学療法士の中北です。
本日は運動学習の概要として、「運動学習の定義」と「運動学習の神経機構の一部」ついてお話いたします。
運動学習とは
運動生理学者のSchmidtは、「運動学習とは、熟練パフォーマンスの能力に比較的永続的変化を導く練習や経験に関連した一連の過程である」と、運動学習を定義しています。
また、ある練習や経験が、ある運動の学習に寄与したという因果関係が特定できるものが、運動学習の概念にあてはまるとされています。
・・・
なんだか小難しいので、例で考えてみましょう!
例えば、子どもが運動発達を通して、1歳前後に自立して歩けるようになったとします。
子どもの歩行能力の獲得は様々な要素が関与するため、何か特定の練習や経験をさせたから歩けるようになった、という因果関係を説明することは困難です。
Aという介入をしたことで、Bという結果を得ることができた、とは言えないということです。
CやD、E、F、G・・・という様々な要素がか関わっているからです。
つまり、このような発育発達の過程で獲得できる能力などは、運動学習の概念にはあてはまりません。
一方で、運動発達の遅延が見られる子どもに対して、何らかの課題を設定して運動発達を促すような場合は、運動学習の概念にあてはまります。
なぜなら、Aという介入をしたことでBという結果を得ることが出来た、という証明が可能だからです。

また、「一過性の変化」は運動学習の定義からは外れます。
例えば、Schmidtさんの表現を拝借してご説明しますと、
「水を熱すれば沸騰するという変化が生じるが、熱することを止めると元の水に戻る。一方で、生卵を熱するとゆで卵に変化するが、熱することを止めてもゆで卵は生卵には戻らない。」
このように、一度生卵を熱してゆで卵になると、生卵に戻ることはないことを、Schmidtさんは運動学習における比較的永続的な変化だということだと述べています。
より現実的な例でも考えてみましょう。
患者さんがリハビリ室で歩行訓練を行っている場面で、リハビリ室ではセラピストに介助されて患者さんの歩容が改善したとします。ところが、患者さんがリハビリ室を出て、1人で歩いた途端に元の歩容に戻ってしまっていたら、リハビリ室では一過性の変化が生じていただけで、運動学習は成立していなかったということになります。

このように、運動学習では「比較的永続的変化を導く」ということが大切になります。
運動学習の神経機構とは
前述の通り、運動学習は一連の過程において比較的永続的な変化が求められており、その変化は脳内において構築されます。
運動学習が脳内で行われていることを表す実験として有名なのが、右手で行った練習が左手にも転移する実験です。
Kawashimaらは、片手で1分間鉄球を回す課題を与え、何回転できたかを調べたところ、後で行った側の手では、利き手と非利き手ともに、初めて行う運動にも関わらず回転数が多かったという結果になりました。
この実験の他にも、ピアノなど両手操作が求められる運動においても、利き手側で獲得された学習が非利き手側に転移することも分かっており、これらの事実からも運動学習は筋や関節などの感覚受容器で行われているのではなく、脳内で行われていることが分かります。
運動学習には多くの部位が関与しますが、中でも「基底核回路」と「小脳回路」が重要であるといわれています。
基底核回路は、運動を遂行するうえでの順序や運動の組み合わせを制御する回路で、大脳基底核は、大脳皮質で計画された運動プログラムに基づいて必要とされる運動を促通し、不要な運動を抑制する役割を担っています。
小脳回路は、大脳皮質からの情報と運動に関する末梢からの感覚情報を統合して運動を適正化する回路で、小脳は課題を繰り返す間に、中枢神経系にフィードバックされた感覚情報との誤差を検出して修正する役割を担っています。
このように、大脳皮質で計画された運動がちゃんと実行され、実行された運動が計画通りだったのかを照合する役割を担う、大脳基底核と小脳は、運動学習においてとても重要です。
専門家向けのオンライン学習サイト
現在「Pilates as Conditioning Academy」という、ピラティスを活用して目の前のお客様をより良くする為の学習サービス&養成コースを運営しております。
こちらでは、ピラティスエクササイズをはじめ、機能解剖学や運動生理学、神経科学、バイオメカニクスなどをオンラインで学習することができます。
さらに詳しく学び、現場での指導に活用していきたいという方、ピラティスの資格取得をお考えの方は、「Pilates as Conditioning Academy」もぜひご覧ください。
フリー会員登録して頂いた方には、10本の無料動画をプレゼントしております!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
imok株式会社
中北貴之